今日は何の日?
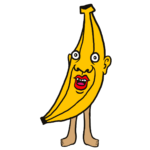 完熟バナナさん
完熟バナナさん今日は完熟バナナがお供しますわ



ツル子さんもねー
4月1日「エイプリルフール」
4月1日は「エイプリルフール」です。
この日は嘘をついて良い日とされていますが、どんな嘘でも許されるわけではありません。
「罪のない嘘をついても良い」とされる日であって、人を傷つけたりするような嘘はついてはいけませんので、当たり前ですが、注意が必要ですね。
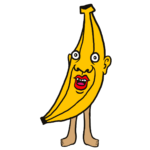
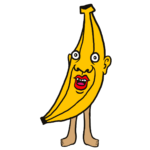
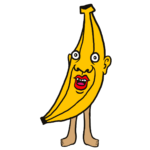
当然のマナーですわね。私が完熟なのは本当ですわよ



そんなの食べてみないとわからないわ!
エイプリルフールの起源はフランス
16世紀のヨーロッパは新年が3月25日で4月1日までの1週間を春の祭りとしていました。
しかし、シャルル9世が1月1日を新年とするグレゴリオ暦を採用すると、急な変更に市民たちが怒り、祭りの最終日4月1日を「嘘の新年」と呼び大騒ぎを始めました。
これにシャルル9世が激怒し、市民たちを次々に逮捕し、処刑。
この悲劇を忘れないように毎年4月1日になると「嘘の新年」として祝うようになったのがエイプリルフールの始まり、という説が最も有力なのだそうです。
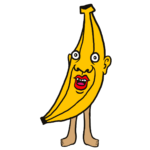
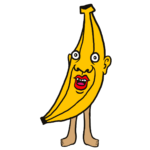
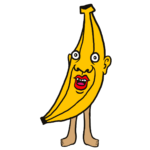
今では楽しむ日だけど、起源は悲しい出来事だったのです



背景を知ると、イベントにも奥行きを感じるわね
逆エイプリルフールがある?
実は13年に1度、嘘をついてはいけない逆エイプリルフールというのが存在すると言われています。
これはエイプリルフールの起源が関係しています。
フランスの暦が変わり民衆の反乱がきっかけで作られたエイプリルフールですが、反乱で処刑された民衆の中にわずか13歳の少女が含まれていました。
市民たちはこの少女への哀悼の意味を込め、少女の年齢に合わせ13年ごとに嘘をつかない、という風習が生まれたのだそうです。
しかし、これには明確なソースがなく、真偽はかなり怪しいとされています。
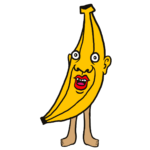
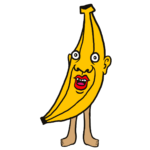
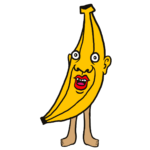
ツル子さん鵜呑みにしちゃだめ!



ワタシはツルだから鵜呑みはしないわ!ツル呑みよ!
エイプリルフールのルール
実はエイプリルフールで嘘をついていいのは、午前中だけとなっており、午後になったら嘘のネタバラシをしなくてはいけません。
このルールは、イギリスで行われる王政復古の記念日がもとになっています。
王政復古の記念日で人々は帽子や襟元に飾りをつけ、王への忠誠と誓います。
しかし、この飾りをつけるのは午前中だけです。
この風習がエイプリルフールにも流用され、嘘をつくのも午前中だけになったそうです。
王に忠誠を誓う風習を「嘘」だと皮肉って、ルールを流用した、という説もあるそうです。
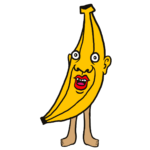
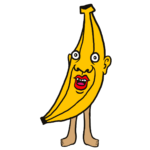
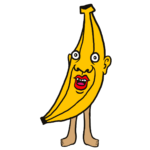
なんだか気の利いた皮肉って感じですわね



アイロニーってやつね
江戸時代では「不義理の日」
現在のエイプリルフールの風習が日本に入ってきたのは大正時代でした。
日本では直訳で「四月馬鹿」として広がりました。
その「四月馬鹿」が広まる前の江戸時代、4月1日は「不義理の日」と呼ばれていました。
これは、日ごろ無沙汰して義理を欠いている人に手紙を書き、不義理を詫びるという日でした。
偶然にも同じ4月1日にこのような日があったのです。
以上、「エイプリルフール」にまつわるお話でした♪
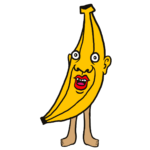
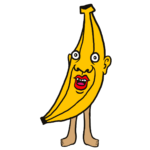
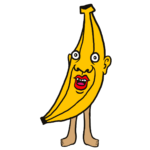
みなさんありがとうね。次回はもっと甘くなって会いましょう。



完熟さん、熟れすぎたらダメよ!

コメント